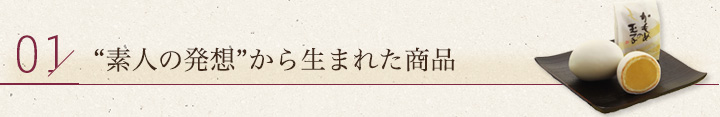かもめの玉子誕生秘話

大船渡の小さな菓子店だった「齊藤菓子店」が昭和二十七年に開発を始め、いまや東北を代表する銘菓に成長した「かもめの玉子」。しかし、現在の味と形にいたるまでには、さまざまな挑戦と失敗、そして工夫と発想の転換がありました。
「かもめの玉子」の誕生秘話をお届けします。
はじまりはばあちゃんの手作りの味

創業当時の店舗(昭和28年頃)
さいとう製菓のルーツは、現会長・齊藤俊明の祖母キヌエばあちゃんの手作りの味にさかのぼります。
キヌエと夫の政治は、岩手県の県南の村・東磐井郡折壁村(現室根村折壁)の大きな農家でした。ところが養蚕で大失敗してしまいます。すべての財産を失った2人はその後、となり村・大原(現大東町大原)の深い山奥に入り炭焼きを始めました。細々と生計を立てていましたが、昭和8年、大船渡の鉄工所で働いていた次男俊雄のすすめを受け、町に出ることに決めました。
三陸の大きな港町・大船渡。町には活気があふれていました。ちょうど大きなセメント工場も建設されていて、齊藤家の前は毎日、大勢の作業員が通りました。キヌエは、その人たち相手に、手作りの大福やもち、ゆべしなどを売る商売を始めました。キヌエの作る味は評判を呼び、「齊藤餅屋」はとても繁盛したのでした。
戦争中休業していた「齊藤餅屋」が商売を再開したのは昭和23年のことでした。それには、「食べ物商売はどんな時代でも安定している。商売は信用が大切」との、キヌエの考えがありました。作業場は廊下を改造した、わずか一坪の空間。家族みんなで協力しあい、もち菓子作りを始めたのです。
郷土大船渡の魅力がつまった
観光土産になる新しいお菓子を。
昭和25年ころからは、「齊藤菓子店」の看板をかかげ、和菓子も手がけるようになりました。現会長俊明の父俊雄は、このとき考えました。
〈元々はもち屋で、菓子作りの素人の私たちが、あたりまえの和菓子を作っていても、老舗の和菓子屋さんにはとても太刀打ちできないだろう。何か店の特徴を出し、特色のある菓子を考え出さなければいけない〉
知恵をしぼり、そして思いついたのが、観光みやげとしてのお菓子でした。俊雄は三陸の美しい海をもつ観光地大船渡の魅力は何だろうかと思案しました。思い浮かんだのは、青い海原の上を颯爽(さっそう)と飛ぶカモメの姿でした。そしてすぐに、「鴎の玉子」「沖のかもめ」「五葉松」「うにの子」と、一挙に5つもの商品名を考えついたのです。俊雄はさっそく「鴎の玉子」(のち平成11年に「かもめの玉子」と改称)の商品化に取りかかりました。昭和26年のことです。
俊雄が目指したのは、カモメの玉子の形をしたカステラ饅頭でした。カステラは、卵・砂糖・小麦粉・水あめなどをまぜて焼いた和菓子。このカステラの中に、黄味餡を入れて焼くというのが俊雄のアイデアでした。さらに、齊藤菓子店ならではの味の特徴を出すために、知恵をしぼりました。その結果、カステラ生地にマーガリンを練り込むことを思いつきました。和菓子に洋風食材を練り合わせるというのは、伝統を重んじる純粋な和菓子職人では思いつかない、素人ならではの斬新な発想でした。実際に試作して食べてみると、それまでのカステラの味にまろやかさと、なんともいえない風味がプラスされて、独特のおいしさに仕上がっていました。俊雄は、自信を持ちました。
〈よし、この味ならいける。きっと、たくさんの人に受け入れてもらえるはずだ…〉
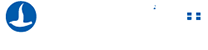



 『かもめの玉子』の生い立ち・誕生秘話・制作秘話
『かもめの玉子』の生い立ち・誕生秘話・制作秘話