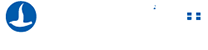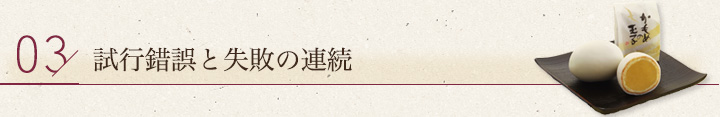かもめの玉子誕生秘話
理想の形とはほど遠い不良品ばかりの日々

クッキーで岩床までつくり本物を追求した
「鴎の玉子」(昭和39年頃)
完全な玉子形で、味も時代に合った「鴎の玉子」をつくろう。俊雄、長男俊明、弟の俊祐は、さまざまな意見とアイデアを出し合い、試行錯誤を繰り返しました。俊明は試作のたびに、素材の配合表を細かく記録し続けました。その結果、鉄板で焼いても比較的玉子形を維持できるのは桃山(黄味あんを焼いてつくる和菓子)の生地でした。これに、白い粉糖グラッセ(粉砂糖に卵白を混ぜたもの)をかけることで玉子の殻に見立てることにしました。味の面では、あんの生地にコンデンスミルクを新しく加えることで新しい味を創出することに成功しました。
現在の「かもめの玉子」につながる過程の中でもっとも大変だったのは、まんじゅうを本物の玉子形に焼くための機械の開発でした。まんじゅうを桃山製にすることで、初代のカステラ生地の商品より、ずいぶんと玉子形に近づいてはいたものの、鉄板で焼くため、まだ下の部分に偏平状態が残ってしまっていたのです。
齊藤菓子店(のち昭和54年「さいとう製菓」として法人化)は、二代目「鴎の玉子」の売れ行きが好調でした。そこで、より理想的な形にするため昭和41年、機械を導入しました。イカせんべいの焼き機を改良したもので、玉子形に成型する型を取り付けたものでした。
ところが焼き終わったあと、製品を取り出すために型を開くと、上半分と下半分の型に生地が付着して、玉子が半分に割れてしまいます。何度試みても、うまくいきません。
また試行錯誤が始まりました。型に油をいっぱい塗ったり、生地にマーガリンを多く人れてみたり、まんじゅうの表面に粉をいっぱいまぶしたり…。出来上がってくるのは、理想の形とはほど遠い不良品ばかり。ある日、今度はまったく別の方法で焼いてみようということで、成型の型を本体から取り外し、それをオーブンに入れて焼いてみました。すると、その形は亀の甲に近いものでしたが、鉄板で焼くよりもましな玉子ができました。1カ月ほど、その方法で焼き続けるうちに、しだいに型になじみ型離れしやすくなってきました。俊明は「これはひょっとしたら機械に取りつけてもうまくいくかもしれない」と思いました。成型を本体に取りつけ、何度も試行錯誤を繰り返すうちに、「ポイントは温度にありそうだ」という、直観めいたものを感じ取っていったのです。
やっとたどり着いた理想的な玉子形
それは昭和42年3月末のことでした。俊明がいつものように実験を繰り返していると、あるとき、成型からひとつの玉子がきれいにはがれました。
「あっッ!」俊明は、思わず声をあげてしまいました。きれいに剥離したのは、その1個だけではありませんでした。成型を斜めにすると、次々と玉子を取り出すことができました。試作を繰り返すうちに、まんじゅうと成型がなじんできたこともありましたが、やはり温度がポイントであることが確信できたのでした。
俊明は、さらに実験を繰り返しました。いったん型をある温度に上げ、そこで油をしいて型の表面に油膜をつくる。それから温度を下げ、ある定まった温度になったときにまんじゅうを入れて焼くと成功することにたどり着いたのでした。
現在、「かもめの玉子」の製造工程の主な流れは、次の要領で行われています。
- 【練り】原料をよく練り合わせ、玉子の生地をつくる。
- 【包あん】黄味あんを中央に配してカステラまんじゅうをつくる。
- 【焼き】玉子形の型に入れて焼き上げる。
- 【コーティング】玉子の殻に見えるようにホワイトチョコでコーティング(昭和39年から)
- 【包装】冷却したもの